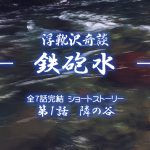浮靴沢奇談 鉄砲水
【第5話 鉄砲水】
前回からの続きです。
【第1話 隣の谷】はコチラ。>>
【第2話 浮靴沢】はコチラ。>>
【第3話 河原にて】はコチラ。>>
【第4話 靴の淵】はコチラ。>>
淵には茶色の世界が広がっていた。
濁りだった。
僕が河原にへたり込んでいたしばらくの間に淵は濁ったのだ。
勿論、大岩の存在すら、既にわかるような状態ではなかった。
言葉がなかった。
こんな間の悪い出来事もないだろう。
なぜ、今なのか…… そして、何が起きたというのか……
考えてみなければいけなかった。
この濁りの中に隠れている、その本質の部分がいったい何なのかということを。
それは、到底、今、僕が気にしているような淵底の物体などのことではなくて、もっと別なものであるということを。
けれど僕は、ここでもまた、それに気付くことができずにいたのだ。
そして、後から思えば、このような己の能天気(のうてんき)ぶりこそが、恐らく『あれ』の出現を招いたのかもしれなかった。
僕が依然として、虚しいような、恨めしいような、そんな心持ちのまま、ただただ淵の濁りを眺めていた時のことだった。
とにかく、それは出現し、一転、今度はその存在が、僕の意識の全ての部分を瞬時に支配した。
『靴』だ。
一足が滝の方から流れて来たようだった。それから、良く見るともう一足、滝つぼの辺りにも浮いているように見えた。
途端に、頭の中が真っ白になり、何も考えることができなくなったが、その直後なのか、数分が経過したのかわからないけれど、ふと我に返り、まずはもう一度、見間違いじゃないのかと疑ってみる。
けれど、やはり靴に見える。子供が履くくらいの靴に見える。
僕にとって、それは金歯のでっち上げのはずだった。
「そんなバカなことはない。もう少しこちらに寄るのを待って、しっかりと確かめよう。」
しばらくの間、ゆっくりとこちらへ近づいて来る、その靴らしき物の行方を、じっと目で追っていたけれど、ふと、むこうの滝つぼ辺りにも浮かんでいた、もう片方が気にかかり、今度はそちらへと目をやった時のことだ。
この大きな淵の頭の流れ込みとしては、どうしても不釣り合いに思えてならなかった、先程までの、あの、か細く小さな滝が、今は “ ザー ” という音を立てて、勢いよく茶色の水を吐き出しているではないか。
そして、あろうことか、その滝つぼには、一足、また一足と、大量の靴が際限なく浮かび始めていたのだ。
「何なんだ! 夢でも見ているのか!? どれだけ流れて来るというんだ!」
「まさか、本当に鉄砲水が来るとでもいうのか!?」
自分の理解も想像も、全てのつじつまが合わなくなったかのような状況の中、ガタガタと震え始めた足は持ち主の言う事を聞かなくなって、遂には力が抜けて、僕はヘナヘナと河原にしゃがみ込んだ。
ところが、だ。
ただ呆然としていた、僕のぼやけた視界の隅に、その時、何かが “スッ” と、滑り込んで来た。
「枯れ葉!?」
それは枯れ葉だった。まるでビワの葉のように、立派な木の葉が一枚、そこに漂っていた。
靴は、靴ではなかった。それは一枚の枯れ葉に姿を変えて、ここへと流れ着いたのだ。
「…… なんだヨ、勘弁してくれ!脅かしやがるぜ、まったく!」
「枯れ葉を靴と見間違えるなんて、俺も案外ビビリだな。オヤジのせいで、ちょっと神経質になりすぎたか。」
「なんだほら、靴なんか一足もないじゃないか。全部枯れ葉だ。本当にビックリさせやがる。」
そんなふうに、我ながらお粗末すぎる話だと苦笑したのも束の間のことだ。
安堵のため息をつくことなど到底許されない事態であることは、すぐに分かった。
そして、一度は緩んだ緊張が再び僕を襲い、今度は石の様に固まって、動くことすらできなくなった。
水の濁りと、大量の枯れ葉。
きっと、上流の支流かどこかで、流れが堰き止められていたのだろう。昨日よりずっと川の水位が下がっていたかもしれないということも、この時は、ようやく想像することができた。
淵は、おびただしい量の枯れ葉に、埋め尽くされ、それと同時に、水嵩はみるみると増して来ていた。
生け簀の魚達が、淵へと解き放たれて行くのが見えた。
自由になった魚達に代わって、今度は自分がこの淵に捕らわれたかのようだった。
「でも、靴は無かったじゃないか。だからきっと大丈夫。なにも起こるはずがない。」
そんなふうに自分に言い聞かせてみても、やはり体は自由に動いてはくれなかった。
「靴は無かったじゃないか。」
「靴など見ていないじゃないか!」
叫んだ声は、上流からの川風に流れて消えた。
そして、これまで以上に強い川風が吹きおろしたかと思った、その時のことだ。
突然、辺りが少しだけ明るくなって、淵を取り巻く全ての音は消えて行き、僕は不思議な静寂の中に包まれていた。あの激しさを増した滝の音さえ聞こえることはなかった。
「命を失ったのだろうか?」一瞬、そんなことを考えていた時……
!!
突然、誰かが、僕の背中を、“バン!”と叩いたのだ。
すぐ後ろに、人の息づかいを感じる。
振り向くことすらできない僕の後ろで、その誰かが、大声を上げた。
「来るよ!」
――ハッと目が覚めたような感覚とともに周囲の音が蘇って来たのがわかったけれど、その後のことはあまり良く覚えていない。
車に戻った時には既に日は暮れていた。
ロッドは持ち帰ることができていたものの、慌ててあの淵の斜面を登ったのだろう、その先端は、ポキリと無残に折れていて、それから妙に左腕も痛んだ。
到底、川の様子を伺ってみようという気持ちにはなれなかった。
けれど、それでもやはり、鉄砲水は来たのだと思う。
辺りには土埃のような、一種独特な匂いが立ち込めていた。
少し落ち着きを取り戻したように感じても、『あの声』を思い出すだけで、途端にまた胸の鼓動は高まった。
はっきりと聞いた。男の子だった。
早くこの場を離れたいと思う気持ちと、心細い気持ちとで、オヤジの宿を目指す。
今日の事を話せば、そら見たことかと罵られるのか、それとも鼻で笑われるのか。
ところが、いくら車を走らせてみても、夜のせいなのか、それともまだ気が動転しているせいなのか、いっこうに宿を見つけることはできない。
何度か行ったり来たりを繰り返した後、道端に雑草の生い茂る少し開けた場所を見つけ、車を止めると、そこでタバコに火をつけた。
「おかしいな。この辺りではなかったか?」
(even)
【第6話 日差しの中で】へ続く。>>