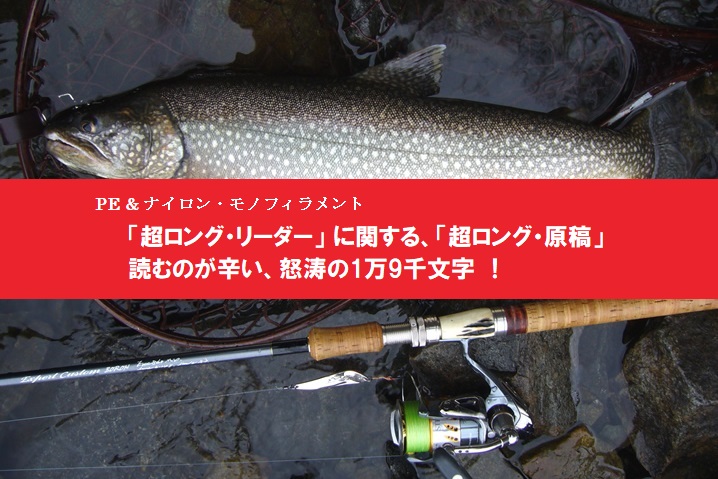
PE & ナイロン・モノフィラメント
「超ロング・リーダー」に関する、「超ロング・原稿」 読むのが辛い、怒涛の1万9千文字!
Kガイドでも、Yガイドでも、トラブルレス!
~ PE&10メートル・超ロング・ナイロンリーダーの勧め(編集部)~
【本文は、PEライン1~1.5号、リーダー10~16LBS程度を使用した、スピニングタックルによる、主に、湖のトラウトフィッシングや、本流の大鱒、遡上魚などの釣りを想定した内容で構成されていますが、その他のジャンルの釣りにおいても参考にしていただけたら幸いです。】
少しでも減らしたいPEラインのデメリット
皆さんは、PEラインで、何のためらいもなくルアーをフルキャストできていますか?
なにかとライントラブルに悩まされることの多かったPEラインでしたが、2009年頃、ロッドへの糸がらみ低減を実現した、「Kガイド」の登場も一役買って、PEライン人気は加速、今日に至っています。
ロッドのほうも、ナイロンラインであれ、フロロカーボンラインであれ、そしてPEラインであれ、要するに使用できるラインの自由度を高めるための様々な工夫が施された、ガイドや、ガイドセッティングのものが登場しています。
ただ、そんな現在の状況においてもなお、意外と根強くライントラブルは発生しているもので、「トラブルが完全になくなることはあり得ない」ことを念頭に置いておく必要はあるのかもしれません。
少し極端なお話しですが、PEの糸がらみが原因でロッドを折ってしまった苦い経験から、どうしてもキャスティングが遠慮がちに。。そんなかたがいたりもします。
今なお、「扱いが難しい部類のライン」と言わざるを得ないPEラインですが、とても魅力的であることに違いはありません。
メリットを生かし、気持ちの良いロングキャストで楽しみたいものです。
今回ご紹介するラインシステムは、10メートルもの、「超ロング・ナイロンリーダー」を使用することで、スピニングタックルにおける、PEライン使用時の不具合を低減させることを目的としたもので、PEラインのデメリットを補う、いくつかの面白いメリットを持ち合わせています。
また、「Yガイド」に代表される、ごくスタンダードなガイドを装着した、旧式のスピニングロッドなどの場合では、「PEラインの釣りには向かない」と、糸がらみなどのトラブルを恐れて敬遠されることも多いのですが、これらのロッドであっても、実用上、PEラインの使用が可能となる場合が多いことも大きな特徴です。
『 勧め 』と言っても、「ロング・リーダー最強!」とか、そういうお話しではありませんのであしからず。。
(以降、ライントラブル軽減を謳った様々な特徴を持っている最近のロッドや、そうしたガイドシステムに対し、「Yガイド」に代表される、ごくスタンダードなガイドや、それらを装着したロッドのことを、便宜上、「旧」、「旧式」、「古い」などと表現させていただきますことをご容赦ください。)
旧式スピニングロッドも使用可能なラインシステム
さて、繰り返しとなりますが、やっぱり、PEラインって難しいです。
ロッドの長さやアクション、使用するルアーの種類や重量などによって、相性の良い(ライントラブルの少ない)リーダーの長さは、マチマチだったりするし、どのような釣りをするのかによってもラインシステムは変わってきます。
「つい先ほどまで、順調にキャスティングできていたのに、少しリーダーを詰めただけで、いきなりトラブルが発生しだした」などという経験をされたかたもいらっしゃるかもしれません。
自分の釣りに合った、安定したパフォーマンスが発揮できるシステムを見つけるまでは、それなりにライントラブルがあったりするわけです。
だから、アングラーの数だけラインシステムがあると言っても過言ではないし、それ故、人によって、言うことがぜんぜん違っていたりもします。
さて、なかなか本題に入れずに申し訳ないですが、ここで一つ、クイズです!
25年前の6月のこと。
秋田県 米代川、待ちに待ったサクラマス解禁。(この頃の解禁日は6/1でした)
その年、『PEデビュー』に胸を躍らせていた僕(編集部)の実話です。
準備していたタックルとラインシステムは、以下のとおり。
・ロッド:UFMウエダ スティンガーディープボロン SST-82-H(Yガイド)
・リール:スピニングリール シマノ ステラ・ミレニアム4000SS
・PE(メインライン):バークレイ・ファイヤーライン 16LBS(1号)
・リーダー:ナイロン 12LBS 数メートル(ノット部はリール内に巻き込み)
・ラインシステム(ノット):ビミニツイスト&オルブライトノット
・ルアー:フローティングミノー
Q:夜明けを待って、満を持しての第一投! さて、どうなったでしょう?
気を取り直しての第二投! どうなったでしょう?
三投目も四投目も。。何度やっても。。どうでしょう?
A:はい、その通り! 何度キャストしても、PEとリーダーの結束部(ノット部)が、ガイドに絡んで飛んでいかない。10回投げれば、10回絡む。
そ~っと、そ~っと、“フワリ”とやっても、それでも絡む。まぐれでも成功しない。
ミノーを掴んでそのまま放り投げたくなるほどで、全く使いものになりませんでした。
あわてて、現場でナイロンに巻き替えましたが、かなりのショックを受けましたし、この時は何が悪かったのかさえ、まったく理解できずにいました。
時代は、トラブル低減を謳った「Kガイド」登場以前のことです。
今回ご紹介する、10メートル・リーダーシステムの考え方は、このお話に端を発するもので、僕の場合は、現在に至ってもなお、このラインシステムを使い続けていますし、もちろん、上記、米代川でのロッドやリールをそのまま使った場合でも、あの悪夢のような出来事がウソであったかの如く、快適な釣りが実現できています。
それでは、ここで、上記の解説と、システムの具体的な仕組みについて、ご説明したいと思います。
まず、ガイドにラインが絡む要因の一つに、PEラインとリーダーの結束部である、「ノットの重量」が関係しています。
リールにリーダーを巻き込んでいる場合のお話しになりますが、キャスティングをおこなうことによって、ライン(リーダー部)は、リールのスプールに巻かれていたラインの束の中から、ほぐれながら、スパイラルの軌跡を描き、放出されていきます。
この放出されたラインの「暴れ」を最初に収束させて整える役目を持つのが、「バットガイド」なのですが、あの時の米代川でも、膨らむラインの回転運動を順調に絞り込んでいたはずのバットガイドに、その後すぐ、例のノット(この時は、ビミニツイスト&オルブライトノット)が迫り来るのです。
ノットがスプールから解放された次の瞬間、このデカくて、ゴツくて、重~い、ノットの塊による、急激すぎる重量変化とその遠心力によって、ラインの膨らみは一気に増幅し、途端に収拾がつかない程に、バタバタと暴れまくります。
加えて、そんな事故現場に、今度は重量の軽いPEラインまでもが、どんどんと送り込まれて来て、Yガイドに絡みついた。というわけです。
ですから、ここで、最初に重要なポイントは、
「なるべく小さく、重量を抑えた、ライトなノットを採用すれば、ライントラブルを減らすことできる。」ということです。
ただし、ライトなノットで、PEとリーダーを接続すれば、「PEの強度はノット部で半減する」と言われるほど、PEのノットはデリケートなものになりますので、どんな結びかたをするかは、悩ましいところです。
ちなみに僕の場合は、今のところ、摩擦系の、「変形フィッシャーマンノット」で落ち着いています。
もし、ロング・リーダーに拘らないのであれば、「ショート・リーダーにして、あらかじめノット部をトップガイドの外へ出しておく」というのが、「この事象のみ」を考えるうえでは、一番シンプルな解決策かもしれません。
(余談ですが、最近のロッドは、ガイドリングが小型化される傾向があり、そのせいもあってか、ノット部はトップガイドの外に出すように推奨しているメーカーもあったりするようです。
ライントラブルを回避する主旨での「推奨」なのだと思いますが、ショート・リーダーを推奨すること自体、釣り方の制約、ひいては、良くも悪くも、それによる釣果までもが影響を受けるものであり、僕個人としては、「推奨」と言うには、若干、行き過ぎたものを感じざるを得ませんが、そのロッドが、そういう仕様であるのなら、「あえてロング・リーダー」という選択は避けるべきかもしれません。)
次に、たとえ旧式ガイドのロッドであってもPEの釣りが成立するしくみをご説明するうえで、そもそも、なぜ、PEラインはトラブルが多いのかを考えてみると、概ね、以下の2点があると言えます。
① ライン放出時、ノット部の重量変化でラインが暴れやすい。(前述)
② ラインが細く、軽く、張りがない為、「糸さばき」が悪い。
例えば、糸撚れ、糸フケ等で、「くねくね・ふわふわ」と落ち着きがなくなり、ロッドテップへの「巻きつき」や、「キンク」が起こりやすい。
同様に、リール・スプール内に、糸撚れ、巻きムラ等があると、「もつれ」や、「バックラッシュ」を発生したりする。
Kガイド等の、PEに対応した最近のガイドは、ご存じのとおり、「物理的に引っかかる場所を無くしてしまえ!」の発想ですので、残念ながら、上述①などでラインが暴れた際の、ライン放出抵抗そのものは解決できておらず、依然として残っている場合があります。
この対応策としては、
・ガイドを少し前傾させてあげましょう!
・バットガイドも少し小さくしたほうがいいかもね!
くらいの感じです。
ガイドリングに対するラインのすり抜けに関してだけを考えた場合には、かえって旧式Yガイドのほうが、リングがラインの進行方向に対し素直に正面を向いていて(前傾すると、リング形状は、実質的に円ではなく楕円。開口面積も減る)更にはリング径自体も大きいので、「ロングキャストにおいて、理にかなっている」と言われることもあるほどです。
(最近のガイドには、色々な工夫も見受けられますが。)
そして、当然ながら、上述②を防ぐことはできません。
つまり、たとえ旧式ガイドのロッドであっても、ノット部の軽量化に加えて、何らかの方法で、①をキチンと解決できればそれで良いことになります。
そして、②の「糸さばき」についても、「もう少し何とかしたい。」と思うわけです。
ということで、ようやく本題の、「10メートル・超ロング・リーダーの勧め」です!
ポイントは二つです。
【 その1 】
キャスティング時のラインの放出スピード(ルアーの初速)が落ち着くまでは、ノットを外に出さない。
通常(システムを組まない)のナイロンラインによる、Yガイドロッドでのキャスティングと同様に、ナイロンリーダーが勢いよくガイドを抜けて行き、その後、ラインのスパイラルによる遠心力が弱まり、ノット部の自重によるライン挙動への影響が無視できるくらいまで落ち着いたタイミングで、軽く小さなノットがスルスルと穏やかに、ガイドをすり抜けていく。そんなイメージです。
ガイドとの強い摩擦によるノット部の痛みが少ないのもメリットと言えます。
【 その2 】
キャスト直後(シュート中)のロッドティップの振幅(ブレ)が落ち着くまでは、ノットを外にださない。
同じ考え方ですが、ティップがブレているうちは、ラインも振られて暴れています。
振幅が減衰した後のタイミングで、ノットがガイドをすり抜けていくイメージです。
要するに、リーダー10メートル分のタイムラグにより、問題解決を図ろうという理屈です。
また、リーダーを長くとることで、②の「糸の、さばきにくさから生じるトラブル」についても、一部、改善が可能ですので、ここでもう一度、②の不具合を思い出してみたいと思います。
② ラインが細く、軽く、張りがない為、「糸さばき」が悪い。
例えば、糸撚れ、糸フケ等で、「くねくね・ふわふわ」と落ち着きがなくなり、ロッドテップへの「巻きつき」や、「キンク」が起こりやすい。
同様に、リール・スプール内に、糸撚れ、巻きムラ等があると、「もつれ」や、「バックラッシュ」が発生したりする。
ロッドティップへの糸絡みは、様々なシチュエーションで発生しますが、絡んでいる状態に気付かないまま、ルアーをキャストしてしまった場合が、一番深刻かもしれません。
ルアーが軽ければまだしも、もし大きな衝撃がロッドに加わることがあれば、最悪の場合、ロッドが破損します。
また、キンクやバックラッシュに関しても同様で、キャスト直後のライントラブルにはとかくリスクが付きものです。
これに対して、ナイロンは、太くて張りがあるため、扱いやすく、完全ではないとしても、同様のトラブルは、かなり低減させることができます。
つまり、ナイロンラインのフィーリングそのままにキャスティングが行えることが強みです。
また、「もつれ」や、「バックラッシュ」の原因となる、リール・スプール内部での、糸撚れ、巻きムラの抑制にも一定の効果があると言えます。
PEラインは、その「くねくね・ふわふわ」とした特質から、「糸フケが出やすいライン」だと言うことができます。
だから、ルアーをキャストした後には、今度は、この「くねくね・ふわふわ」の状態のラインをそのまま巻き取ってしまわないように極力注意しなければいけないわけですが、これがなかなか難しい。そんなシチュエーションが、案外多くあるものです。
例えば、止水域、向かい風の中で、i字系のような、引き抵抗がほとんど発生しないようなルアーをスローリトリーブしているにも関わらず、ラインテンションをかけながら、リール内に整然と綺麗にラインを巻き取って行くことは可能でしょうか?
このような時、少しでも、ラインにテンションがかけられるだけの、何らかの抵抗感がほしいと思うはずです。
つまり、この抵抗を、重量があって、太さもある、10メートル分のナイロンリーダーが賄ってくれるということです。
また、後述しますが、PEラインは、糸がフケていると、魚のアタリが出ません。
一般に、PEと比べ、感度が悪いと言われるナイロンラインですが、このように、ラインテンションを得やすくすることで、PEの感度が生きてくるということもあるのです。
そして、ラインがきれいに巻き取りやすくなることで、リール系のライントラブルが減るというわけです。
まだあります。
仮にリール内のPEラインの部分に何らかのトラブルの「種」が発生していたとして、キャスティングによる、ロング・リーダー放出の後、ラインスピードが衰えてからのPEラインのトラブルであれば、ロッドへの衝撃が少なくて済むと言えますし、同時に、もつれたPEラインをほどくのも、比較的、楽である場合が多いです。
(リールのスプール内のPEラインに糸撚れが発生していると、キャスト時にラインがもつれてしまうことがあります。僕は、なるべくPEラインに糸撚れを入れないようにするために少し注意していることがあります。
これに関しても、文末の、『おまけ 1 ロング・リーダー活用編』にて触れましたので、参考にしてください。)
ここまでは、10メートル・超ロング・リーダーのシステムを組むことが問題解決のポイントであることをご説明してきましたが、実は、僕はナイロンラインが大好きで、どうしても、そのメリットを重要視してしまうので、実際のところPEラインの出番というのは、かなり限定的で、湖や本流のトラウト、サクラマスなどの遡上魚等、主に、大物を岸から狙うような釣りの中で、特に飛距離を稼ぎたい時や、根ズレ対策として、リーダーが必要な時など、PEラインの使いみちは、せいぜいそのくらいに限定されています。
だから、この、超ロング・リーダーのシステムも、タックルバランス的にオールマイティーとなり得るものではないかもしれませんが、僕の場合、今どきのロッドの必要性を感じることはほとんどなく、Yガイド装着の旧式ロッドで、ミノーでもスプーンでも、ほぼ、ノンストレスな釣りが成立していますから、そういった意味でもライントラブルの少ないシステムと言っていいと思います。
ちなみに、僕が所有しているYガイドロッドのうち、現状、PEラインの使用頻度の高いものは以下の2本で、どちらのロッドも、とても古いものです。
・UFMウエダ・スティンガーディープ ボロン SST-82-H
(しなやかな82 前記、米代川のロッド)
・イトウクラフト・エキスパートカスタム ボロン EXC 860 MX
(シャキっとした強めの86)

これらのロッドで使用するラインは、PEが1~1.2号、リーダーは、「リーダー専用」として販売されているものではなく、通常の100ヤード巻きナイロン・モノフィラメントの、12~14LBS程度のものです。
(使用するスピニングリールのハンドルを何回転させると糸巻量10メートルに相当するのかを把握していると、便利です。)
もし、お手持ちの旧式Yガイド・スピニングロッドを使用してみようという場合には、「どこまで応用が利くか?」、是非ご自分の釣りに当てはめて検討してみていただきたいと思います。
ナイロンラインの長所が生きる、10メートル・超ロング・ナイロンリーダーシステム
さて、ここからは、「ライントラブル回避」という視点とは全く別の角度から、このラインシステムを見ていきたいと思います。
ナイロン素材、それも、ある程度の長さがあってこそ初めて発揮される、「超ロング・ナイロンリーダー」のメリットについてです。
このシステムは、一言で表現するならば、良くも悪くも、PEラインとナイロンラインのハイブリッド感が強い、「平均点」のシステムと言うことになります。
つまり、PEの良さ半分、ナイロンの良さ半分です。
「凧の足」のように10メートルものリーダーを引っぱりながらルアーが飛んでいくさまは、高切れしたルアーが、ブッ飛んでいくようなイメージに近く、通しのナイロンと比べれば飛距離は伸びるものの、通常のPEラインのシステムに比べて、それ以上に飛ぶということは当然ながら、ありません。
よって、飛距離に全振りした、ピーキーな個性を得ることはできませんが、その代わりに、PEラインの短所をナイロンラインの長所で補えるという良さがあります。
では、ナイロンラインの良さって、何でしょうか?
フロロはどうでしょうか?
リーダーの長さが、5メートルだとダメでしょうか?
最初にリーダーの長さですが、結論から先に申しますと、ロッドやルアーの自重など、使用するタックルの性格によって、切り詰められるリーダーの長さの限界長は変わってくるのですが、「トラブル回避だけ」であれば、もっと短くても大丈夫な場合が多いと思います。
実際、前述の旧式ロッドを使用した場合でも、根ズレ等があれば、そこから一ヒロ、また一ヒロと、リーダーをカットするのですが、「そろそろ限界だな」と感じたことはあまりありません。
だから、「もう少し、ロングキャスト寄りのセッティングで!」と言うことであれば、最初から5メートルとかのリーダーシステムで様子を見てみるのも良いかもしれません。
ただし、この時に切り詰めたのは、「リーダーの長さ」だけではなく、同時に「ナイロンラインの個性」も切り詰められていることにはなります。
「ナイロンラインの恩恵が活かせる、実践的なリーダーの長さ」ということになると、10メートル程度はあったほうが、良いのではないかと考えています。
具体的なナイロンラインの長所、他の素材のラインとの違いに関しては次章で、「超ロング・ナイロンリーダーシステム」のメリット解説と合わせて、お話しさせていただきたいと思います。
だから、ナイロンリーダー 10メートル!
「ナイロンの長所」をどれくらい踏襲したいかで、リーダー長を決めてみる。
世は多様性の時代。
最近では、いきなりPEの釣りから入る人、フロロばかりを使うアングラーなど、様々です。
しかし、ナイロンラインにも根強い人気があますし、エキスパート・アングラーの中にも、ほぼ、「ナイロン一択」という方がいらっしゃったりします。
ナイロンラインの魅力を知るうえで、ここではまず、スピニングタックルの使用を前提に、PEライン、ナイロンライン、フロロカーボンライン、各々の性質の違いの中から、注目したい点を整理したいと思います。
一部、すでに説明済みの項目を含みますが、ご容赦ください。
(ラインの価格面や、強度、耐久性、温度特性 等、本題からそれた特徴の比較は割愛します。)
【 PEライン 】
長所:
・細い。ロングキャストに向いている。(対ナイロン)
・伸びがないので、リーリング中など、ラインテンションがかかった状態においては、感度が非常に高く、明確にアタリや、水中障害物などの情報を感知できる。
・伸びがないので、フッキングパワーの伝達ロスがない。
短所:
・糸さばきが悪く、ガイド絡み等のライントラブルに注意する必要がある。
・糸フケがあると、感度が悪く、当たりがとれない。
・クッション性がない。(伸びがないので、振動、衝撃の吸収がない)
クッション性がないことによる具体的なデメリットには、次のようなものがあります。
(ただし、使用するロッドの強度、リールのドラグ設定などを弱めることで、改善できる場合があります。)
・バイト時の反動が強く、はじかれてフックアップしなかったり、浅掛かりになったりすることがある。
・ファイト中の衝撃が魚へダイレクトに伝わるため、魚が暴れやすい。
また、魚の損傷(針穴が広がる、身切れする)により、バラシのリスクが高まることがある。
・魚への反動が大きいため、バレやすい。
・強すぎるアワセでは、口切れ(身切れ)し、フックアップに至らない場合がある。
【 ナイロンライン 】
長所:
(ナイロンラインの長所は、基本的に、上記、PEラインの短所をカバーする内容です。)
・糸さばきが良く、ライントラブルが少ない。(対PE)
・使用ロッド(ガイド種別)を選ばず、汎用性が高い。
・糸フケがあっても振動が伝わるので、アタリが取りやすい。
・クッション性がある。(弾力があり、適度に伸びる)
クッション性があることによる具体的なメリットには、次のようなものがあります。
・バイト時の食い込みが良く、魚のノリがいい。
・魚に対してソフトで、魚が暴れにくい。
・ファイト中の魚の動きにラインの伸縮が追随するので、ラインテンションが抜けにくく、魚がバレにくい。
・浅掛かりでも、口切れ(身切れ)によるバラシが少ない。
短所:
・太い。飛距離で劣る。(対PE)
・クッション性があるため、感度がソフトで、ダイレクト感で劣る。(対PE)
・伸びる分、フッキングパワーの伝達ロスがある。
(ただし、フッキングパワーのロスに対しては、使用するロッドの強度や、リールのドラグ設定などを強めたり、ドラグが出ないようにスプールを手のひらで押さえてからアワセを入れるなどで改善できる場合があります。)
【 フロロカーボンライン 】
フロロの基本的な特徴は、それが長所であるのか、短所であるのか、一概に言えないところがあり、素材の特質を理解した上での、適材適所の使いみちという感じです。
本題からは少しそれるのですが、簡単に触れておきたいと思います。
・伸びが少ない。(対ナイロン)
・硬い(対ナイロン)
・太い(対ナイロン)
フロロは硬いので、キズ自体が入りにくく、根ズレに強いと言われています。
ただし、その分もろいので、一度入ったキズからは、案外、呆気なく切れるのがフロロだったりします。
(ガラスのイメージ)
対して、ナイロンは潰れやキズが入りやすいですが、弾力があるので、キズが入っていても、多少の粘り強さがあります。
(ゴムのイメージ)
(少し極端ですが、上記のカッコ内は、各素材に対する、僕の持つイメージです。)
ここまで、基本的な各ラインの素材ごとの特徴の違いを見て来ましたが、PEラインを使用した釣りの中で、是非とも付加したい性能が、ナイロンラインの「伸びる性質」つまり、「クッション性」よる「バレにくさ」であるということが、ご理解いただけるのではないでしょうか。
それではここで、先ほど「ナイロンラインの恩恵が活かせる、実践的なリーダーの長さは10メートル程度と思われる。」と申しました、その理由について、考えていることを以下にご説明したいと思います。
同じパワーの魚に対して、使用するナイロンラインが細ければ、「短くても伸びてくれる」と言えますし、太ければ伸びにくいわけです。
魚の警戒度や、ゲーム性などの理由で、あえてラインを細くすることもあるとは思いますが、通常であれば、狙う魚のサイズやパワーと、使用するラインの太さは比例すると思います。
そして、ナイロンラインのみを「通し」でリールに巻いて釣りをすることと比べてみると、ナイロンリーダーを使用する場合には、おそらく、それよりも太く、強いものを選択する場合が多くなると思いますし、ナイロン部分の全長も当然ながら短いわけですから、「ナイロンラインが伸びる量」つまり、「クッション性」も、ナイロン本来の感覚と比較して「少なくなる場合が多い」といえます。
ところで、「魚は、寄せてからがバレやすい」と思いませんか?
なぜでしょうか?
理由は多くの要因が絡み合っているとは思いますが、以下に思いつくところを少し、列挙してみたいと思います。
・アングラーが魚の視界に入ることで、より一層、激しくファイトしだす。
・魚からロッドティップへと伸びるラインの成す角度が開く(大きくなる)ことで、魚の口元に、それまでとは異なる向きからの力がはたらき、フックが外れる。
(例:魚の動きに合わせて、ロッドを左右に切り返したりする際など。)
・岸からであれば、寄せたことで、水深が浅くなり、魚が水面に出やすくなる。
〇 時間の経過とともに徐々に魚の損傷が大きくなる。
(針穴が広がってきたり、身切れしてきたりする。)
〇 魚のヘッドシェイクなどで、ラインテンションが抜ける。(緩む)
このような感じではないでしょうか?
上記のうち、リーダーの長さを決める際に考慮したいのは、〇印をつけた、最後の2つなのですが、これらは、たとえ魚をバラシにくいとされるナイロンラインで釣りをしていたとしても、防ぎきれない場合だってあるわけです。
「魚が近づけば近づくほど、また、出ているラインの長さが短くなればなるほど、ナイロンですら、そのクッション効果が減少し、バラシのリスクが高まる」とも言えるかもしれません。
ですから、「自分から半径10メートルの範囲内くらいは、せめても、ナイロンラインで魚とのやりとりがしたい。」もしくは、仮に遠くでヒットした場合であっても、「そのように想定できるくらいのナイロンリーダーの長さがほしい」というわけです。
そして今度は、フッキングパワーの伝達に関してですが、ラインにクッション性を求めれば求めるほど、また、ナイロンリーダーが長くなればなるほど、フッキングパワーの伝達ロスがあります。
ただ、すでにお分かりいただけたかもしれませんが、「伸びない」と言われるPEラインの先端に結ばれているナイロンリーダーが10メートルだとすれば、仮に遠くで魚が掛かったとしても、アングラーの立ち位置から、10メートルそこそこの近場でアワセを入れたのと同等の伝達パワーがあることになります。
(厳密には、近場の魚へ届くパワーに比べ、沖の魚へ届くパワーは、PEであれナイロンであれ、ラインが受ける水圧の分だけロスします。)
例えば、岩場などで根掛かりが多く、フックポイントを常に鋭い状態で管理しきれない状況下であるとか、バスフィッシングに例えるなら、フロッグを用いた釣りであるとかであれば、ナイロン10メートル分のフッキングパワーのロスが仇となることがあるかもしれませんが、通常のシチュエーションであれば、使用するロッドにもよりますが、ほぼ、問題のない範囲ではないでしょうか?
考え方は、だいたいこのような感じですが、もちろん、「ナイロンリーダー 10メートル」は、あくまでも「一つの目安」と、捉えていただいて結構です。
是非、ご自身のフィッシングスタイルに合わせた、ベストなリーダー長を決めてみてください。
環境への配慮について
繰り返しになりますが、「リーダーとの結束部で、PEの強度は半減する」と言われるほど、PEのノットはデリケートです。
最近では、高強度かつ、コンパクトに仕上がるノットのお話しなども聞きおよぶことがありますが、ノットの劣化なども考慮すると、やはり、「50パーセント程度まで落ちる」と認識しておいたほうが良いような気がしています。
もし、ルアーが根掛かりをして、それを回収できず、この結束部から切れてしまったらどうでしょう?
仮にショート・リーダーであったとしても気がとがめるところですから、それこそ「超ロング」を、そっくり水中に残してしまうなどということは、絶対に避けなければなりません。
実は、幸いなことに、10メートルリーダーであれば、比較的、高確率でルアーを回収可能です。
そして、もし回収できない場合でも、リーダーを水中に残すことなく、ルアーの結び目から切れてくれることが多いです。
どのような対象魚に対して、どのようなスタイルの釣りをするかによっても全く変わってしまいますので、「絶対」ということではありません。
ただ、根掛かりが発生した状況では、リーダーとPEラインの結束部は、「すでに手元まで来ている」ということが意外に多いのです。
僕の場合であれば、湖や本流での話となりますが、根掛かりするのは、圧倒的に手前のブレイクライン近辺に集中していたりするのがその理由です。
どうしてもルアーが外れない場合、リーダーに手が届きさえすれば、PEとの結束部に負荷をかけることなく、リーダー強度をフル活用して、「根掛かりとの力比べ勝負」を挑むことができるので、ルアー回収の確率が高まるというわけです。
「力比べ勝負」に勝てなかった場合は、リーダーに傷さえ入っていなければ、ルアーとの結束部からラインが切れます。
一例ですが、表層を狙った岸からのキャスティングなどのように、沖での根掛かりを気にしなくても良いような場合や、仮に根掛かりしても、ウェーディングすればリーダーまで手が届く状況などであれば、これは「メリット」として捉えることができます。
ただし、ここからが本題です。
「もし、リーダーに手が届かなかったらどうするか?」です。
リーダーとの結束部で、PE強度は50パーセントにまで落ちているとすれば、仮に20LBSのPEラインなら、強度10 LBSで「勝負」しなくてはいけません。
例えばこの時、12LBSのリーダーを使用していたとして、もし、ルアーが10 LBS以上の強度で結ばれていれば、「リーダーを水中に残す可能性がある。」ということです。
だから、この場合であれば、ルアーへのノットは、「パロマーノット」などの、強いノットを避け、あえて「弱いノット」を使用することになります。
また、少しお話しがそれますが、もし、これと全く同じ状況であれば、僕の場合、リーダーを10 LBSまで落として対応するという選択は、なるべくなら、しないようにしています。
理由としては、摩擦系のノットを使用する際、10 LBSというリーダーの細さは、あまりにも「コシ」がなく、「ノットを美しく仕上げ、常に安定した強度を保つのが意外に大変」と感じているからです。
もう、お気づきのかたもいらっしゃるかと思いますが、環境面を配慮した際、「強すぎるリーダーを選択できない」のが、「あまりにも長い、超ロング・リーダーの欠点」です。
そして、僕の場合であれば、「コシのない、弱いリーダーも使いにくい」。。
だから、上記の例では、もし、「ルアーとの結束強度が、10LBS以下では不十分」ということになると、必然的にPEの強度から上げていかなくてはならなくなりますし、「PEの強度は上げずに、リーダーだけをもっと強く(太く)したい。」となれば、代わりに、ルアーとの間にスペーサーとして弱い捨てリーダー(例えば10LBSリーダー等)を、数十センチ程度付加する(テーパーリーダーを組む)などの配慮が必要になってきます。
(リーダーの性能として求められるのは、「強さ」はもちろんなのですが、根ズレ対策を考える場合などには、「太さ」のほうがより重要になってくる場合もあります。
最近のナイロンラインは優秀で、同一強度でもワンランク細いものなども多いですが、僕がこのシステムを使用するうえでは、前述の欠点を踏まえて、「同一強度でも、あえて、なるべく太いラインを選択する」ということがあります。)
ところで、「結ぶべきリーダーの号数は、使用するPEラインの号数の4倍程度が適当である。」というお話しを、時々、耳にすることがあります。
4倍です。
僕の場合、これは少し悩んでしまいます。
もし、PEラインが1号で20LBSなら、リーダー4号は16LBSくらいでしょうか?
PE1.5号が30LBSなら、この時は、リーダーは6号で、何ポンドでしょう?
「たとえフックを伸ばしてでも、ルアーは絶対に回収する!」が、叶えば良いのですが、「最低限、ラインは水中に残さない」だとすれば、安定した「80パーセント・ノット」くらいは是非ともほしくなるところです。
僕にとっては「鬼門」であり、「先祖返り的」な、「ビミニツイスト&オルブライトノット」や、さすがに、ダブル・ラインは大袈裟だとすれば、せめて「ボビンノツト」程度は必要になってくるかもしれません。
また、それに対応できるように、タックル全体のバランスも見直す必要がでてくると思います。
4倍号数のリーダーが必要となる対象魚や、そういうシチュエーションがあるのは当然のことですが、もし、そのよううな場合であれば、特別慎重にラインシステムは考えていくことが必要となりそうです。
最後に
「PE & 10メートル・超ロング・ナイロンリーダーの勧め」、いかがだったでしょうか?
大体、こんなところです。
「超ロング・リーダー」に関する、「超ロング・原稿」 読むのが辛い、怒涛の1万9千文字!
もし、最後まで読んでいただけたかたがいらっしゃいましたら、それはもう、「超・感激」です!
少しは「なるほど!」と思っていただける部分があったでしょうか。。?
そこのところは、「超・不安」です。。
PEって、やっぱり難しいです。
アングラーの数だけラインシステムがあると言っても過言ではないし、それ故、人によって、言うことがぜんぜん違っていたりもします。
これは、冒頭でも触れた言葉ですが、やはり、悩みはつきません。
でも色々と考えてみるのは案外楽しかったりもします。。
それではまた!
快適なPEフィッシングを楽しんでくださいね!
(even)
そうそう、忘れてました!
「おわり」と見せかけて、、と、言うわけではないのですが、システムの具体的な活用事例など、少し実践的なところのお話しをさせてください。
かなり限定的なシチュエーションなので、「おまけ」ということでお願いします!
(おまけにしては、また、ダラダラと長いですが。。汗 )
おまけ 1 ロング・リーダー活用編
~ 使ってみて気づく、10メートル・超ロング・ナイロンの、プチ・メリット ~
・PEの糸撚れを防ぐ。
ご存じのように、リールの構造上、スピニングリールを使用する限り、糸撚れは避けられません。
ですから、少なくとも「その他の要因による糸撚れ」に関しては、なるべく避けて、ライントラブルは極力減らしたいところです。
ここでは、スプーンを使用した本流での釣りの中でも、特に糸撚れが発生しやすい「逆引き」で、僕が実行している「ロング・リーダーを利用した、糸撚れの軽減策」をご紹介したいのですが、その前に、糸撚れに関しても、PEラインとナイロンラインでは、かなり性質が異なりますので、まずはそこからご説明したいと思います。
PEラインの撚れは、案外、厄介だったりします。
にもかかわらず、「PEラインは細いので、撚れにくい」と言われることがあります。
実際は、「ラインに張りがなく、大変柔らかいので、ラインが撚れていても馴染みやすく、実害が起こりにくい。」が、正しい表現ではないでしょうか?
糸撚れしていても、最初のうちは、気付きにくいとも言えます。
ただし、これも限度の問題で、撚れが蓄積されて大きくなってしまうと、今度は、キャスト時にラインがもつれてしまうなどの、案外、深刻なトラブルが発生しだしたりします。
PEラインはそれ自体に弾力がないので、一度、撚れが入ると、それを戻そうする反力があまり働きません。
撚れたら撚れっぱなしということです。
だから、アングラーが能動的に何らかの手段を講じない限り、一度入ってしまったラインの撚れは取り除くことができず、蓄積されるいっぽうになってしまいます。
(回避方法として、ロッドをクルクル回したり、専用の道具を使用するなどが知られています。)
これに対して、ナイロンラインに撚れが入った場合は、例えば、ロッドから垂らしたルアーがクルクルと、かなりの勢いで回転したり、ゆるんだラインが交差するように巻き付き合うなど、撚れによる影響が出やすい反面、比較的早く、その状況に気付くことが可能と言えます。
この現象は、ナイロンラインが撚れたことによって生じる、反力によるものです。
ライン自体に弾力性があり、「入った撚りを自分で戻そうとする復元力」があるということです。
ですから、限度の問題はありますが、ラインの先端に「スイベル(ヨリモドシ)」さえ付いていれば、ゴム動力の模型飛行機がプロペラを回すように、ナイロンラインは、自らスイベルを回転させて、撚りを戻していこうとするわけです。
さて、ここから「本流釣り」のお話しでしです。
本流の釣りでは糸撚れに注意が必要です。
ダウンの釣りや、アップクロスにルアーを投げて、それがダウン気味となり、U字を描き、最終的には逆引きになるようなシチュエーションでは、特に注意します。
流れに逆らってルアーを引いてくる際、性能の良いミノーであれば、回転することも、水面を割って飛び出すこともないので、これ自体による糸撚れの心配はないですが、同じ状況でも、スプーンでの釣りとなると、ルアーに回転が生じ、ラインが撚れます。
だから、スプーンの場合、スナップで接続せず、スイベル(ヨリモドシ)単体をリーダーに取り付け、これを、スプーンのスプリットリングの隙間から挿入してセットしています。
これだけでも、糸撚れはかなり回避できますが、まだ完全ではありません。
水圧が大きく、スプーンの回転が激しい場合などでは、どうしてもライン側へと撚りを伝えてしまいます。
(右回転、左回転が、リーリング中や逆引きの際に、スイッチ(切り替わる)するような性能をもつスプーンがあり、このようなスプーンの中には、スイベルを付けないほうが良いものもあるので、注意します。)
「スプーンがU字を描き、最終的には逆引きになる」そのようなシチュエーションは、全リーリング工程の後半で生じる状況なので、超ロング・ナイロンリーダーを使用する場合であれば、リーダー部分に大半の撚れが集中することになります。
前述のとおり、「PEラインへの撚れの蓄積」は厄介ですから、ロング・リーダーよりも奥側の、PEの部分にさえ大量の撚れが入らなければ、それだけでもかなりのメリットと言えるのですが、問題は、その次のキャスティングにあります。
この状態からルアーをキャストすると、それが飛んでいく間、空中に浮いているナイロンリーダー部が、その撚れをほどこうとするのです。
つまり、スイベル側に撚れを逃がすだけなら良いのですが、柔らかなPEライン側にも撚りを入れることで、自分の撚れを逃がそうとするのです。
こうして、PEのほうにも一部の撚れが伝わってしまうわけです。
そして、この運動が何度も繰り返して続くと、PEに蓄積されていた撚れは、どこかのタイミングで、もつれて、「ボソッ」と固まった状態で放出されてしまうことがあります。
ですから、僕の場合、「PEライン側に糸撚れを伝えないようにするための対処法」として、「可能な限り、ショートレンジへのキャストを織り混ぜていく」ということを意識しています。
時々、リーダー部だけを放出させる程度の、つまり10メートル以内のショートキャストを行ってあげるのです。
これで、リーダーの撚れは、スイベルのみを回転させて、ほぐれていくことになります。
PEラインを使用するうえでの、ごく限られたシチュエーションではありますが、多少なりとも効果を感じることができる、超ロング・リーダーだけが持つメリットです。
・ルアーの位置を把握する。
リーダーとPEラインの結束部は、例えコンパクトなノットであっても、案外目立つものです。
つまり、ルアーから10メートル離れた位置に、「目印」があることになります。
リーリング中、例えルアーを目視できなくても、おおよその位置が把握できるので、これは本当に便利です。
例えば、ブレイクラインや障害物などと、ルアーとの位置関係がわかることで、根掛かりを低減できます。
本流であれば、ルアーのトレースコースのコントロール精度があがります。
例えば、「あの岩の上流側にルアーを通してターンさせたい。」のようなことも比較的簡単にできるようになります。
・糸フケを低減させる。
PEラインは、とても軽いので、水流や風の影響をうけて、ラインが大きく膨らむように流されたり、フケたりしてしまいがちです。
水の比重以上の重量を持つナイロンのロング・リーダーによって、これらを低減させる効果があります。
(僕はPEラインにおいても、最近ではよく目にする、高比重のものを使用しています。)
こちらも本流などでのお話しとなりますが、押しの強い流れの中でも、比較的、ルアーのトレースコースをコントロールしやすいですし、ミノーを使用したトゥイッチングなど、糸フケを利用したアクションをかける際には、流されたラインに引っ張られて、ミノーの頭が不用意に下流側へ向きすぎてしまうのを防ぐので、「ナイロンでは、ルアーのアクションにキレがなくなるのでは?」という心配も、思ったほどではないような気がしています。
・バレを防止する。
これは、すでにご説明済みですが、あえてもう一度。
特にサクラマスのバレ対策には有効だと思っています。
恐ろしいほどのヘッドシェイクとローリング、口元も案外もろいですから、サクラマスをPEで獲ることを難しいと感じているアングラーは多いと思います。
ただでさえ確率の低いサクラマス。
ヒットしたのなら何とか捕りたいところですが、ロングキャストや感度など、ヒットの確率を高めるうえでの、PEのメリットと、バレやすいというデメリットを天秤にかけて、あえてPEを選択しているという状況のアングラーも多いです。
僕の場合は、ロングキャストを捨て、ナイロンの「通し」で挑むか、このリーダーシステムと併用して、できるだけしなやかなロッドで、ゆるゆるのドラグ、そして、ドラグが出ないようにスプールに手を添えてアワセを入れるなどでの対応が多いです。
ただし、不用意にドラグを滑らせると糸撚れが入るので、少しだけ注意しています。
・根ズレに耐える。
そして、最後にもう一つ。
PEラインは、根ズレにとても弱く、リーダーを使用するのは、「当たり前」と言えますが、例えば、ダウンの釣りで、ラインを下流へ流していくような場合や、テトラ帯など、ロケーションによっては、ロング・リーダーゆえの安心感が、そのままメリットになることがあります。
通常であれば、「むやみに長いリーダーは、飛距離や感度を損ねるので、得策ではない」との考えから、避けられる傾向にありますが、「むやみに、ただ長いわけではない」ということは、わかっていただけたのではないでしょうか?
おまけ 2 釣果編
~ロング・リーダーで、“ 獲ったど ”~
ルアーライフの過去記事にあるものの中から、「PE & 10メートル・ナイロンリーダーシステム」による釣果のご紹介です。
【メモリアル・フィッシュ】

【魚類剥製の作り方】より 記事はコチラ!>>
【最近の釣果】

2025-6-23【拘りの“スタッグ&PEラインシステム”で、利根マスに挑戦して来ました。】より
(even) の独り言
もちろん、PEも好きです。
でも、何と言っても、ずぅ~と前から、ナイロンラインが一番、使い勝手が良いと思っているのです。
まぁ、ずぅ~と前なら、釣り糸と言えば、ナイロンくらいなもんで、今のように幅の広い選択肢があったわけではないのですが、とにかくナイロンラインが大好きなのです。
ただ、ナイロンは、品質管理がかなり大事なのでしょう。
特に、湿気は大敵らしいですね。
「パッケージの台紙が適度に湿気を吸ってくれる。」そんな役割も果たしているのだと、メーカーのかたから聞いたことがありますが、当然ながら、あまりにいい加減な管理では限界があるかもしれません。
以前、どうしても入手できなかったラインを、ネットで見つけて購入したことがあるのですが、もう、高切れの連続で、ウッドベイトから、オールドのルアーから、チューンしたプラグから、あれもこれも、かなりの数のルアーが、帰らぬ人となってしまったことがあります。人じゃないけど。
まったく、どのような在庫管理がなされていたのかと思うと、それから、もし、大物に切られたりしたら。。などと考えると、ほんとに恐ろしいです。
信頼できるルートから入手することは、大切かもしれません。
あと、普段、自宅では、桐箱に入れて一眼レフ用の湿気とりと一緒に保管しています。
その点、PEは安定していますね。
先日、僕的には大好きなPEなのですが、あまり人気はなく、なんと、停滞在庫の処分で半額になっているのを見つけたので、買い占めました。
複雑な心境ではありますが、ラッキーでした。
フロロは、市場に出回り出した頃、呉羽(現クレハ)の「シーガー」を試したのですが、僕の場合は長続きしませんでした。
当然ながら、今は当時と比較して、色々と性能も上がっているのだと思うのですが、何とも。。

▲ 手前は、超Old! 50年程前のナイロン・モノフィラメントラインで、僕にとっては限りなく原点に近い、デュポンのストレーン。
僕が知る限り、ダイワはもちろんのこと、ティムコが扱っていいた時代のモノよりも更に古いのか、デザインが異なっていて、100ヤード巻きでもこの貫禄です!

▲ 比較的高比重なPEで、ナイロンラインユーザーも違和感少な目で使用できる、ラパラのサフィックス832。少し太めですが気にしていません!
1/8本分のゴアファイバーが最後の一本になっても皮一枚繋がってくれるという、超ギリギリながらの安心感?






